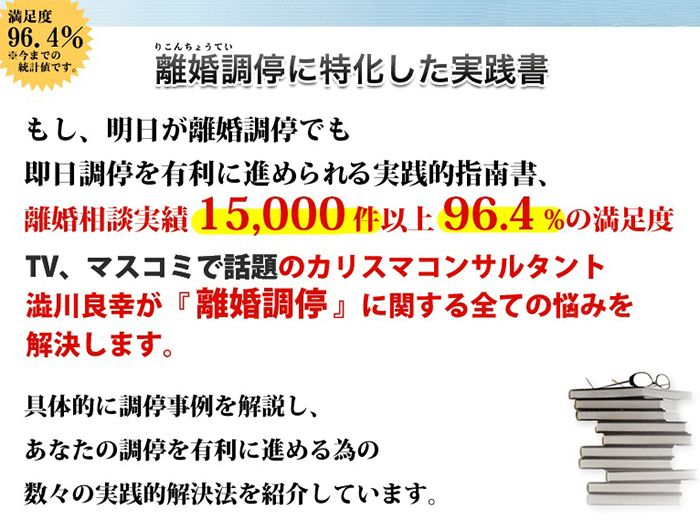離婚財産分与において、住宅ローンが残っているオーバーローンの場合について解説します。
離婚した後も、所有名義や債務や保証人が自動的に解消されることはありません。
パターン別に解説しますので、しっかりと把握しておきましょう。
住宅ローンが残っているオーバーローンの場合は、この住宅に経済的価値がないと判断されます。まだ自分たちの財産になっていないということです。
ローンの残った住宅は、手放す場合と維持する場合で、解決策が異なります。
住宅を手放す場合
住宅を売った後に残るローンというのは、財産ではなく負債にあたります。
負債については、財産分与の対象とならず、各自がそのまま責任を負うことになります。
ローンを組んだ名義人や保証人は、そのまま責任を負うということです。
財産分与に該当しないため、離婚後に、半分の負債になったり、保証人から外れるということはありません。
離婚後にどちらが支払っていくかを協議したり、支払えないため破産などの方法を検討することになります。
住宅を維持する場合
夫婦どちらかが、ローンの残った住宅に住み続ける場合です。
この場合も、住宅には価値がないことになりますので、財産分与の対象とはなりません。
ローンも保証人もそのまま、ということになります。
ただ、この場合、出て行くほうが保証人になっている場合は、保証人から抜ける方法をとるのが通常です。
保証人から抜けられないケースもありますが、できる限り、保証人から抜けるよう協議を行っていきましょう。
妻が連帯債務者・連帯保証人になっている場合
住宅ローンを組んだ際に、妻が夫の債務の連帯債務者・連帯保証人になっているケースです。
離婚をしても、金融機関との契約は変更されません。
もし、主たる債務者である夫がローンを支払わなかった場合、
連帯債務者・連帯保証人である妻が、金融機関から支払いを請求されることが考えられます。
この場合、金融機関に相談して、連帯債務者・連帯保証人を解除する必要があります。
具体的には、以下のような方法があります。
- 住宅ローンの借り換えをする
- 住宅ローンの支払期間などを見直す
- 別の方に連帯債務者・連帯保証人になってもらう
別の方に連帯保証人になってもらう条件や、どういった条件で連帯保証人を解除できるかなどについて、金融機関へ相談しておきましょう。
連帯債務者・連帯保証人のままで、金融機関から住宅ローンの支払いを請求されるとなると、お子様の人生までにも影響が及びます。
連帯債務者・連帯保証人になっている場合は、離婚前に解除することを検討されてください。